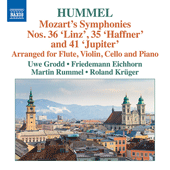音楽聞き放題サービスが発達してきたおかげで、レコード芸術に掲載されている新譜の多数を簡単に聴くことができるようになりました。このブログでは、レコード芸術を読んで気になった盤を聞き放題サービスでチェックした感想をメモしていきます。大きめのジャケット写真をクリックするとAmazon Music Unlimitedに飛びます。小さいほうをクリックするとNaxos Music Libraryに飛びます。
◎【039頁】モーツァルト: 交響曲第36番、第35番、第41番〔フンメル編曲による四重奏版〕
ウーヴェ・グロット (fl) フリーデマン・アイヒホルン (Vn) マルティン・ルンメル (Vc) ローランド・クリューガー (p)
交響曲第36番《リンツ》を聴いた。ヴァイオリン、チェロ、フルートは脇役で、ピアノが中心となるアレンジ。楽器間のバランスやフレーズの受け渡しがスムーズにいかない箇所が多数あるように感じてしまったが、これはおそらく、演奏のせいというよりも、もともとの編曲のせいだと思う。ただしピリオド楽器で演奏すればもう少しバランスよく聞こえるかもしれない。
第三楽章の付点音符のリズムにやや甘いところがあるが、それ以外は概して小気味の良いリズムで活き活きと演奏されている。
(2019年7月6日記)
◎【062頁】J.S.バッハ: ブランデンブルク協奏曲 (全6曲)
シギスヴァルト・クイケン指揮 ラ・プティット・バンド
佐伯茂樹氏による今回の「レコード誕生物語」は、ブランデンブルク協奏曲、その中でも特に第2番に焦点をあて、使用されているトランペットとその奏法の歴史をたどったもの。大変勉強になった。クイケンの新盤は、長い管を巻いただけで指孔のないバロック・トランペットを使用し、高次倍音を唇の調節で操ることで音階を得る「クラリーノ奏法」を復活させて演奏した世界初のアルバムだという。そこで、この第2番と、同じく唇の調節だけでホルンを吹ききった第1番を聴いてみた。
これは素晴らしい。すべて唇で調節しているせいか、トランペットもホルンも大変柔らかく音がつなげられている。ハンド・ストップ奏法を用いていないため、ホルンの音色も一定している。さらにこの盤では、チェロのパートを肩掛けの「ヴィオロンチェロ・ダ・スパッラ」、コントラバスのパートを「バス・ド・ヴィオロン」で弾いているため、響きがとても軽やかで、独奏楽器群の綾が低音にマスキングされずよく聞き取れる。楽器や奏法の限界にある種の我慢を強いられることなく、音楽そのものに浸ることができ、かつ、音楽情報の細かい箇所まで自然に聞き取ることができるこの演奏、おススメだ。
(2019年6月24日記)
◎【118頁】シューベルト: ピアノ・ソナタ第21番 / 即興曲集 D.899 / 《白鳥の歌》~セレナード (リスト編)
カティア・ブニアティシヴィリ (p)
ピアノ・ソナタ第21番の第1楽章と、即興曲集第2曲変ホ長調を聞いた。ブニアティシヴィリというピアニストの名前は近年よく目にしていたが、聴いたのは初めて。
いやあ、凄い演奏。演奏の評者お二人ともこの演奏が唯一無二であることを強調していらっしゃるが、本当にそうだ。ソナタ第1楽章では表情が千変万化し、先が読めずに非常に緊張を強いられる。即興曲集では、拍節感をほとんど感じさせず、無窮動のメロディが本当にあたりを漂っているような錯覚をおぼえた。ちょっと怖くなったため、ケンプの古典的演奏を直後に聴き、耳をリセットしてしまいました。こういう怖い演奏を聴き通すことは私にはちょっと難しい。
ところで、使用されているピアノは何なのだろうか。録音の評者が「柔らかでありながら一音一音の切れ味のよさや粒立ちのよさを聴かせる」と書いておられるが、これは録音技術だけでなく楽器それ自体の特徴でもあると思う。スタインウェイだともっときらびやかな音になると思うので、たぶん違うのだろう。とてもシューベルトにふさわしいしっとりした音だ。
(2019年6月22日記)
◎【126頁】J.S.バッハ: 平均律クラヴィーア曲集第2巻
セリーヌ・フリッシュ (cemb)
評者の濱田氏は、個性的なおもしろ味には欠けるが「完成度は高い」と評されている。那須田氏も、「新鮮な閃きや霊感の点ではもう一つ」ながら、「楽曲そのものに親しむには好個の模範的演奏」と評されている。
このような評価を読み、この演奏を進んで聴こうという気になる読者はどのくらいいるのだろうか。私は、バッハの平均律クラヴィーア曲集に対する理解を深めたいのであればファースト・チョイスとすべき盤だと思うので、強く推したい。
確かに一聴して強い個性は感じないかもしれない。しかしバッハの場合、聴き手が曲をきっちり理解していないと、強い個性の演奏はかえって迷惑となる危険がある。例えば、アゴーギクが非常に柔軟な演奏を聴いて拍がわからなくなった経験はお持ちでないだろうか。フリッシュの演奏は、曲想に合わせたテンポの微妙な揺らぎはあるが、それを超えることはなく、かつ、基本となるスピードが速めの場合が多いので、拍節がわからなくなることはまずなく、全体の構造の把握もしやすい。各声部の聞き分けも特に苦労せずできる。各曲の様式の違いも的確に描き分けられている。音もとてもよい。平均律クラヴィーア曲集の曲そのものを理解し聴き味わうのに好個の演奏だと思う。
なお、チェンバロの音は、明晰だが、amazon music limitedで聴く限り、少し金属的にも感じた。第1巻で使用された楽器のほうが落ち着いた音で私は好きだ。
(2019年7月9日記)
◎【127頁】ハイドン / ピアノ・ソナタ集
クリスティアン・ベザイデンホウト (fp)
ソナタハ短調を聴いてみた。使用されているフォルテ・ピアノはヴァルターと息子のレプリカ。ヴァルター製は音がくぐもっていて立ち上がりも鈍いという印象を持ってきたが、この盤の楽器は違う。落ち着いていてやや重い音であることは確かだが、立ち上がりは俊敏だし、音の強さによってかなり音色が変化する。偏見を改めねばならない。第2楽章では提示部リピート時に現代ピアノでいえばウナ・コルダのような音色にされており、繊細な音色を楽しめる。
ベザイデンホウトの演奏はとても素晴らしい。微細なアゴーギクが特に素晴らしく、のびやかに、自然に、音楽が進行する。
なお、演奏の評者の那須田務氏は「とくに任意な装飾音は付けない」と評されているが、楽譜を見ながら聴いたかぎり、多くはないがそれなりに任意の装飾音を付けている。あざとさ皆無の自然な付け方で、とても好印象。
また、録音の評者は「会場の残響が楽器本来の響きを覆してしまい」と書いておられるが、私はそうは感じなかった。もともとヴァルター製のフォルテピアノ自体がくぐもっている音を発する楽器なのでそう感じられたのではないか。
(2019年6月22日記)
◎【182頁】ヤナーチェク: 弦楽四重奏曲第1番《クロイツェル・ソナタ》、同第2番《ないしょの手紙》、リゲティ: 同第1番《夜の変容》
ベルチャ弦楽四重奏団
とても気に入った。ヤナーチェクの2曲は、抒情的な側面を強調するわけでもなく、アヴァンギャルドな側面を強調するわけでもないが、さりとて「中庸な演奏」と評してすませることもできない。評者の相場ひろ氏は「テンポを自在に伸縮させて……それでいて前のめりになることなく、大きく構えた骨太な音楽を築き上げて」おり秀演だと評しているが、私もそう思う。アーティキュレーション、デュナーミク、テンポ、各声部のバランスなどをよく吟味した結果、どんな箇所でも「こうでなければならない」という必然性を聴き手に感じさせるような、洗練された演奏になっていると思う。リズムの鋭敏さも特筆すべき。
リゲティの曲は数十年前に一度聴こうとして途中でやめた記憶がある。当時まだ若かった私は、この曲が単なるバルトークの物まねにしか聴こえず、憤ったのだ。実に久しぶりに聴いた、バルトークにそっくりだという印象は変わらなかったが、バルトークと異なり民族主義的要素がほとんど感じられないことに気づいた。バルトークによくみられる、民謡に端を発するがゆえに独特の抑揚を持ったり変拍子になったりする複雑なフレーズがほとんどなく、その意味でわかりやすいので、楽譜を見ずとも簡単に曲の進行についていくことができる。ベルチャ弦楽四重奏団の演奏が洗練されまくっていることもあいまって、曲の構造が把握しやすかった。
(2019年6月23日記)
◎【182頁】モーツァルト: ピアノ・ソナタ第13番変ロ長調K.333、同第12番ヘ長調K,322、同第11番イ長調K.331《トルコ行進曲つき》
アンヌ・ケフェレック (p)
フレーズの切れ目切れ目に、実にきめ細かく、間を入れたり音を伸ばしたりしている。しかし反対に間を詰めたり音を短くしたりするということはほとんどないため、なんというか、老人の奏でる音楽という印象が立ってしまう。最近になって自分の老いを感じ始めている私にとって、ちょっと抵抗したい演奏だ。とはいっても、音楽の進行が弛緩しているわけではなく、評者の安田和信氏が書かれているように「本当にノーブル」な感じなのだ。これはこれでよい演奏ではないかとも思う。なんだかんだいってアルバムすべて聴き通してしまったし。
なお、安田氏が細部の仕掛けについて特筆されているが、自分には、その意外さに驚きを感じさせられたということはなかった。むしろ、ごく自然に受け止めることができた。トルコ行進曲つきの冒頭につき安田氏は「バス声部の強調が軍隊行進曲風な激しさを演出」していると書かれているが、私にはさほどバス声部を強調しているようには思えなかったし、激しさも感じなかった。むしろ、行進曲風という指示があるにもかかわらずテンポをかなり伸縮させ、デュナーミクの変化もかなりつけていることから、行進曲であることを強調するというよりも、メロディの流れなど、音楽性を強調しているのではないかと思った。ヘ長調の終楽章冒頭の左手和音が分散和音にしている点も、聴き手をびっくりさせるためというよりも、音に広がりと厚みを持たせるための措置と感じられた 。実際、モーツァルトもトルコ行進曲つきでは全楽章にわたり多くの和音を分散和音の形にしているが、それとスタイルを揃えてみようとしたのかもしれない。
(2019年7月1日記)
◎【186頁】バルトーク: 弦楽四重奏曲第2番、ベートーヴェン: 弦楽四重奏曲第11番ヘ短調作品95、ドビュッシー: 弦楽四重奏曲ト短調作品10
ベンユーネス四重奏団
大変素晴らしい。どの曲も基本テンポは速めで、スポーティー。ただし機械的な演奏ではなく、アーティキュレーションとそれに対応したテンポの微調整の吟味が半端なく凄い。凄いにもかかわらず、あまりに自然に聴こえるので注意しない限りその凄さを意識させないという凄さ。調子の良い時のカラヤンを思い出させる。楽譜を見ながら聴かなくても拍節を全く見失わずにバルトークが聴けるというのはなかなか快感である。評者の安田和信氏はドビュッシーについて「しなやかな線がどの声部でも失われず」と書かれているが、ドビュッシーに限らずすべての曲についてそのとおりだと思う。奏者間の音量等のバランスも絶妙だ。
ドビュッシーといえば、今回聴いていて、初めて「なんだかドヴォルザークのアメリカ四重奏曲や新世界を聴いているようだ」と思った。わりとホモフォニックな曲であることや旋法を使っているところからそう思わせたのだろうか。もしかしたら何か面白い考察につながるかもしれないので、忘れないようメモしておいた。
(2019年6月30日記)
◎【223頁】ショパン、リスト、シューマン&アンコール集~HMV録音1925~1937
ヴィルヘルム・バックハウス (p)
バックハウスについては晩年の録音しか聴いたことがなかった。「鍵盤の獅子王」と呼ばれていた若い頃の演奏を聴いてみたいと思いながら機会を得ずに今日まできたが、今回、1928年に録音されたショパンの練習曲集作品10を聴いた。針音が盛大に鳴る古いSPの復刻だが、これでもバックハウス44歳の時。厳密には「若い頃」とはいいがたいが……。
レコ芸の執筆者は「恣意的な緩急を排し、速めのテンポ設定で駆け抜けている」と評している。その通りだと思うが、ザッハリヒにインテンポをキープしているわけではなく、そっけないようでいて実は要所で細かくアゴーギクをきかせており、無機的な感じはしない。また、晩年の録音と同様にピアノが丸みを帯びた音色なので、技巧をひけらかしたきらびやかな印象は与えず、まろやかで熟成した演奏という感想を抱かせる (前のめりのリズムになる曲も若干あるが)。この時もベーゼンドルファーを使っていたのだろうか。比較的若い時においても晩年においても音色が一貫しているところに感銘を受けた。
(2019年6月23日記)